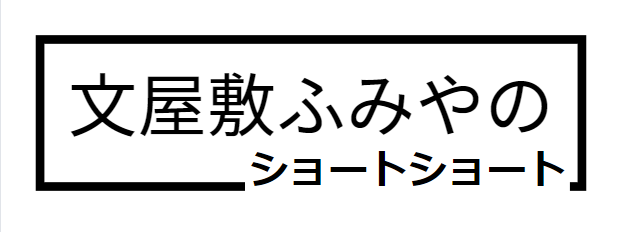友人の家に遊びに行ったとき、ふとテレビ画面に目を向けると、何か映画が流れていた。
何の映画なのかわからなかった。ただ、薄暗い画面の中、人物が動いていて、胸のあたりをナメクジが上っているような、湿った不快感があった。
施設の中で子供を捜し回る登場人物たち。不思議と引き込まれて、言いようのない居心地の悪さがあとを引いた。
その夜、1日目の悪夢を見た。
刃物がこちらに向かってくる。先端がぬるりと胸を貫いた瞬間、飛び起きた。汗だくだった。
2日目の夜は銃で撃たれた。
パーンという乾いた音。体のどこかが崩れていく感触。目が覚めると、汗だけでなく涙まで滲んでいた。
3日目には爆弾を巻かれた。
タイマーがゼロになる。カチ、カチ、カチ――ゼロの瞬間に視界が白くなると同時に、自分もまた目覚めた。
ある夜に、ドアが開いた。
佐藤と鈴木が入ってきた。二人とも疲れた顔をしていたが、僕を見ると、ほっとした顔をしていた。
「お前、ようやく目が覚めたか」佐藤が苦笑いしながら言う。
「何かあった……?」僕は頭を押さえたまま尋ねた。突然痛みだした。
友人たちは苦笑いを浮かべていたが、怒った様子ではない。むしろ何かを隠しているようだった。
「実は、昨日お前の誕生日だったんだよな。だから、ケーキ買っておいたんだ。でもお前がこんなことになっちゃって…まあ、今日になっちゃったけどな」鈴木が笑った。
その笑顔は、どこか嘘のように浮いて見えた。
テーブルには確かにケーキがあった。白いクリームに赤いイチゴ。それを見た途端、胸のあたりが痛くなった。刺されたような、撃たれたような、爆発の後のような。
「俺…本当に目が覚めたのか?」僕は呟くように言った。
佐藤と鈴木は答えなかった。ただ、ケーキに刺されたロウソクが、どこから吹いたのかわからない風で揺れていた。
気づけば、薄暗い映画の画面がまた頭の中に浮かんでくる。施設の中で子供を捜し回るあの場面。どこかで誰かが僕を探している気がしてならなかった。
「おい、山田。食べないのか?」
佐藤の声が遠くに聞こえる。
僕はテーブルのケーキをじっと見つめながら、ただ黙っていた。
――そして、また目を閉じた。