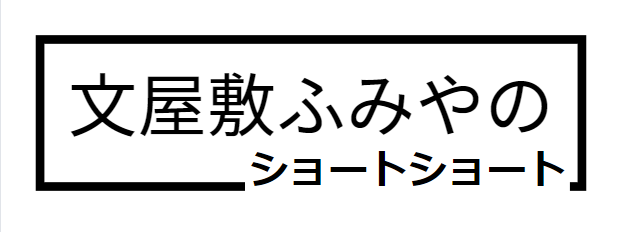口を大きく開けて息を吐いてみる。まだ白い息は現れないかと、澄み渡る秋空の下で僕は思った。
友人の慎太郎に連れられ、僕は遊園地でジェットコースターに乗るべく列に並んでいた。風が冷たいが、どこか穏やかな午後だった。
「ジェットコースターなんて、久しぶりだな」慎太郎が目を輝かせて言った。
「そうだね」
僕は列から見える注意書きの看板を読んでいた。
「ちゃんと荷物を預けるんだぞ。ポケットの中身も忘れずに」慎太郎はわざとポケットの裏地を引っ張り出し、念を押した。
「もちろん」僕は軽く笑った。
アトラクションの順番を待っていると、先に乗っていたカップルが降りてきた。
しかし、彼らはすぐには立ち去らず、女性が何かを探している様子だった。
彼女は座席周りを必死に探し、焦りの色を浮かべていた。男性も手伝い始め、さらに係員まで加わって三人がかりで座席を探り出した。
「何か落としたのかな?」僕は慎太郎に言った。
「スマホとかだろう。注意書きがあろうとやるもんだな」慎太郎が言った。
「でも、スマホだったらもっと必死に探すはずだよ。彼女はすぐに諦めたし、そんなに重要なものじゃなかったんじゃないかな」
実際、その女性は深々と頭を下げて謝り、男性と一緒に係員に軽くお辞儀をしてその場を後にした。
何だったのかと僕たちは首をかしげたが、すぐに僕たちの順番が来たので、そのことはひとまず忘れることにした。
ジェットコースターを降りた後、僕と慎太郎は遊園地内のベンチに腰掛け、軽食を取ることにした。そのとき、慎太郎が妙なことを言い出した。
「ねえ、あの女性、未来から来た人だったりして」
「何言ってるんだよ」僕は笑い飛ばした。慎太郎はジェットコースターで見かけたカップルのことだと、付け加える。
「落としたものが何だったのか。それは未来の技術を持ったイヤリングだったとしたらどう? 身に着けていたものをポケットにしまったんだよ。未来の道具だから荷物を預けるカゴに入れておくのは
心もとないと感じたんじゃないか?」
「未来人でSFなイヤリングだって?」僕は吹き出した。
「そう。例えば元の世界に帰還するための装置が内蔵されているとか」
「それならもっと焦るだろう。ほえれなふ、なるんはぞ」大きな唐揚げを頬張りながら答える。僕は彼の話に付き合うことにした。帰れなくなるんだぞと、伝えたつもりだった。
「俺が推理するに、落としたのはイヤリングの片方だけだったんだよ。イヤリングは両耳につけるものだろう。たぶん、帰還機能は両方ともについているんだ。
彼女はジェットコースターを楽しんだ後、ポケットにイヤリングが2つないことに気が付く。それで慌てて座席付近を探したんだ」
「なるほどー」彼の妄想力にはいつも驚かされるが、この発想にはさすがに僕も苦笑せざるを得なかった。
「イヤリングを探しているうちに冷静さを取り戻した彼女は、片方のイヤリングがあるのだから、帰れることに気が付く。それで、目立つような行動をやめて去ったというわけ」
「でもさ」僕は思いついた疑問を得意げな友人に尋ねてみる。「落としたイヤリングはそのままでいいの、未来の道具なんでしょ?」
「そこはーー。ほら、彼女にしか使えないように生体認証とかついているさ。未来の技術だし、セキュリティは万全よ」
僕は、秋空を見上げここまでの話をまとめてみる。
「イヤリングの片方を落としていたとしても、もう片方を使って帰還できる。未来の道具は彼女にしか使えないから、紛失してしまっても構わない。
彼女と一緒にいた彼はまあ、きっとこの時代で見つけたボーイフレンドって感じかな」
「ああ。紛失自体は彼女自身のミスだし、イヤリングで過剰に騒ぎ立てるのもおかしいと判断したんだろうね。それか彼との時間を優先したのか」
「まったく。ひどい妄想だな」僕は肩をすくめた。
その時、アナウンスが流れた。「紛失物のお知らせをいたします。グリーンエリアの売店付近で、鍵を落とされた方が__」
「イヤリングではなかったな」僕が彼を見やると、彼は考え込むように首が下がっていた。
「あ……忘れてた」
「何が?」僕は首をかしげ、彼に視線を合わせる。
「家の鍵を閉め忘れたかも……ちょっと確認しに行ってくる」
僕の返事を待たずにベンチから立ち上がると、腕時計型のデバイスをいじる。
「おい」
彼はテレポートして家に帰宅した。