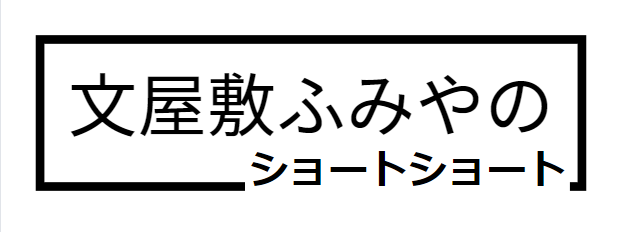「はい、おまちどうさま。とんかつ定食」
定食屋の店長がわざわざ料理を運んできた。今はバイトの人はいないらしい。
「にいさんが新宿にいるなんてめずらしいっすね。仕事ですか?。いや仕事以外で来ないか」
へらへらとしていて猫背で話しかけてくる若者を男はじっと観察した。顔がどこかバッタに似ている。バッタに偏見はないがこの男を信頼できる人間とは到底思えなかった。
「ああ。だが空振りに終わった」
15時を過ぎてガラッとしている店内に、この男の下品な笑いが店に響いた。
「にいさんが逃がすなんて珍しい。ターゲットは同業ですか」
「いや、ただのばあさんだ。俺が行く前にくたばった」
下品な笑いがさっきよりも響いた。そろそろ店長に文句言われるんじゃないかと男は思った。
「死ぬのなんて一瞬すね。おいらもいろんな死を見てきたっすけど、依頼前にくたばっているってのは初めて聞きましたね」
「この仕事をしていれば変わった死に方をする連中を見れるさ。こんな死に方したやつを聞いたことがある。もんじゃにたまたま入っていたキャベツの芯を、のどに詰まらせて窒息死したばあさんがいた。目玉が飛び出るかと思うくらい見開いて苦しそうにそのままくた
ばったらしい」
「うへーいやだね。ギャグにしても笑えない」
笑えないと言いながら、ヘッヘッヘと笑う。笑い方が夏場の公園にいる犬みたいなだなと男は思った。
「ムダな死にっすね。そんな死に方おいらはごめんです」
苦しいのはなおさらと若者は肩をすくめる。
「いや、無駄ではなかったんだ」
「どういうことっす?」
男の強い否定に若者の緩んだ口元がきゅっと締まる。いちいちリアクションが大きい奴だと男は思った。
「ばあさんには娘がいてずっと実家暮らしだ。娘は一人暮らしをしたいし、都会に出たいとも思っていた。でもばあさんは足が悪かったんだ。
といっても歩けないほどじゃない。だがそれを口実に娘に自分の世話を命じた。仕事中の一人娘に毎日毎日電話をしてなにか頼みごとをした。そうすることで娘がいないと生きていけないことをアピールしていた。娘が一人暮らししたいと思っていることに気付いていて寂しかったんだろうな。娘は仕事に、母親の世話で手一杯。彼氏と会う時間もない。とうとう付き合ってた男は娘と別れちまった」
湯呑をいっぱいすする。若者は先が読めたという感じで湯呑を置く前にしゃべった。
「つまりはばあさんが死んだことで娘は自由になれたわけだ。誰かの不幸は誰かの幸福、誰かの幸福は誰かの不幸ってわけっすね」
「そういうことだな」
「ところでなんでそんなに詳しいんです?」
「今日になってその娘からの依頼がキャンセルされたからだ」
「だからこんなところでばったり会ったんすね。じゃあ現場はとなりの鉄板焼き屋か」
謎は全部解けたと若者は箸の束から箸をとりだす。
「なるほどね。キャベツに感謝をこめて、いただきます」
若者は両手を合わせたあと、目の前のとんかつにソースをかけた。男も自分の定食に目を向ける。
すっかり味噌汁からは湯気がでなくなってしまっていた。