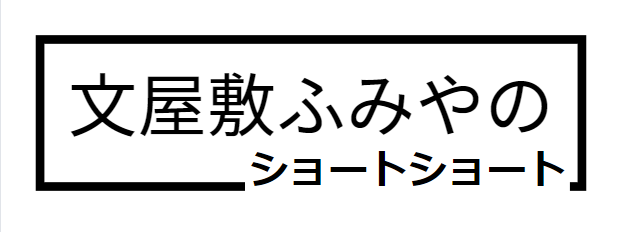死者の眠る墓に咲く花がある。この町の言い伝えの中で有名な部類の話だ。
真っ黒な花弁をもつ美しい花で、それを持つと、死者の記憶を覗き見ることができる。その花は”死神の花”と伝えられていた。
死者の記憶を吸収し、そのエネルギーを花に蓄えるためだとか、なんとか、かんとか……
とにかく都市伝説の域を出ないつまらない話を私は信じてはいなかった。
私がその花を思い出したのは、父の葬式が終わって、半年が経ったころだった。
お墓には先週も来ていた。だから、これはここ数日に現われたものだ。
墓石の手前には言い伝えの通りに咲く、漆黒の花があった。
父の声を聞くことができるようになった。私が眠ると、夢の中で生前の父の記憶を見れるようになったから。
持つだけで記憶が覗けるというのは、デマカセで私自身が眠る必要があった。
死神の花に出会った日、私はそれを持ち帰り自室の花瓶に活けた。
持ち帰ったその日から、ベッドで眠るたびに父の記憶をたどることができた。
物を疑ってかかりがちな私でも3回連続でこんなことが続いたときには、この花の力を疑うことをやめていた。
父の記憶は、私に関することしかでてこない。
最初は私が生まれた時の出来事を父親の視点から見ることができた。
父のその時の喜びも感じた。この花は感情すら体験することができるみたいだ。
次の時は、私が初めて父と母に手料理をふるまった時に事だった。
父の、私に関わる印象的な出来事を、その時の父親になって体験できる。なんだかホームビデオをVR体験をしているような不思議な夢だった。
ある日の夢の中で、父に怒られる私を見た。
東京にある大学に行きたい、と父に始めて言った日だ。あの時のことは今でも鮮明に覚えている。それから三か月後、父は突然仕事中に倒れそのまま息を引き取った。
相談をしたとき私は舞い上がっていたと思う。そして東京というものの存在に、そこに行けるチャンスがある年齢だということに。
なんとなくきらびやかに見える、今とは違う世界にあこがれている。あいまいな、ないものねだりをしている事に父はすぐ見抜いた。
父はオブラートに包むような発言はしない。
殴りつけるように正論を言われ、本当に私にとって必要なことなのかをもう一度考えてみろ、と言われた。
その時私は感情的に父をなじった。父の言葉が正しいことを理解していたからこそ、ひどい言葉を使ってしまった。
きちんと考えてない自分を認めたくなかったから。
それからは、父とは口を利かなかった。
父へ吐いた言葉への罪悪感、もう一度考えた東京に行きたい理由を口にしたとき、また否定されることが恐かったから。
そして父とは二度と話すことはできないままになった。
その夢を見てから、眠ることが怖くなった。
この先眠りについたときに見る夢の中には私が父と話をしなかった時の記憶が再生されると思ったから。
私に対する失望の思いや言葉を知りたくなかった。
死神の花を捨てようとも考えたが、何日ものあいだ凛として咲くこの花を捨てることを罰当たりだと感じていたし、何よりこの花が私を触れさせまいと黒い雰囲気をまとっていた。
人は眠らないと生きていけない。眠気が限界に来た時、私はいつの間にか夢の中にいた。
目の前に母の姿があった。
私は父の目線になりテーブルの先の母を見ている。
「いいんですね」「ああ」
短いやり取りだったが、お互いの決心が感じられた。
「あの子が生まれた時から、いざという時のために貯めていたお金の使いどころが来たんだ」
「あの子は東京に行くかまだわかりませんよ」
「行くさ。今度はきちんと将来を考えて……そういうことができる子だ。相談に乗ってあげてくれ」
「ええ。わかってます」
「ちょうど、新しい業務を任せてもらえそうだったんだ。お金の心配はないよ……酒もやめる」
「無理はなさらないでくださいね」
「ああ、わかってるよ」
夢から覚めた時。頬に涙が伝った。
私が大学へ行くためお金を用意してくれていたことを知った。
父の帰りが遅かったのも、燃えないゴミの量が少なくなっていたことも、何となく気が付いていたのに
私のためにだったなんて考えもしなかった。
父は信じてくれていた。母はそれを知って、あえて黙っていてくれていた。
両親から思いを知り、両肩を強く抱きしめる。
涙を手で拭い、立ち上がってカーテンを勢いよく開けた。朝日が部屋に色を差していく。花瓶に目線を向けた。
死神の花は枯れていた。