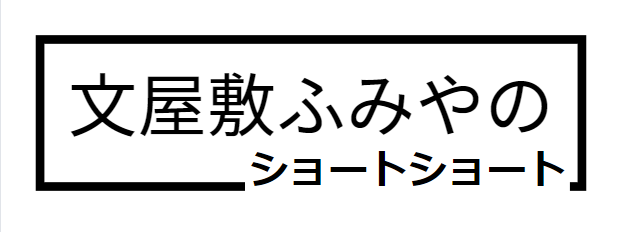木下は久しぶりの再会に胸を躍らせた。社会人になり、同級生と飲みに行くことはほとんどなかった。適当な居酒屋チェーン店で集合し、懐かしい顔ぶれに自然と笑顔がこぼれる。
席につくと、山田と渡辺がすでにビールを片手に待っていた。三人でジョッキをぶつけ、会話が始まる。大学生特有の馬鹿笑いが自然とでてきた。
会話は弾み、次々と運ばれてくる料理と酒。山田が語る新婚生活に笑い、渡辺の愚痴に頷きながら、山田は心の奥で「自分もそろそろ落ち着かなきゃな」と思う。だが、その思考は次第にアルコールに溶かされていった。
「木下、酒強くなったんじゃないか?」
渡辺の声に木下は笑いながら応じた。「家でよく飲んでるからかもな。最近は一人飲みが落ち着くんだよ。」
気がつけば夜も更け、店を出たところから記憶がなくなっていた。
目が覚めたとき、木下は自宅のベッドに横たわっていた。見慣れた天井、しかし何かが違う気がした。頭はズキズキと痛み、喉はカラカラだった。
「どうやって帰ったんだっけ…?」
上半身を起こしてつぶやく。ハスキーと呼ぶにもおこがましい、あまりにも汚い声だった。
ふとテーブルを見ると、小さな青いボタンが転がっている。それを見て木下は眉をひそめた。
「何だこれ…?」
青いボタンは、どこにでもある普通のボタンのようだったが、妙に手に馴染む。触れた瞬間、冷たい感触が指先に伝わる。
昨日あいつらがくれたんだろうか、それとも酒の勢いで買ったものなのか。何かの記念品か、いたずらか。思い出せるはずもなく木下は戸惑いながらも、指先でボタンを押し込んだ。
突然、部屋の景色が歪んだ。まるで水面に投げ込まれた石のように、自分を取り囲む空間が波打つ。次の瞬間、山田は居酒屋の席に座っていた。
「おい、木下、どうした?」
山田が心配そうに覗き込む。佐藤も手を振っている。
「え、え?」木下は周囲を見回した。テーブルには食べかけの唐揚げ、ジョッキには半分残ったビール。まるで時間が巻き戻ったかのようだ。
「酔ったか?」渡辺が冗談めかして笑う。
この状況は何かがおかしい。湧きあがった疑問とともに、青いボタンのことを思い出し、自分のポケットを探る。しかし、そこにボタンはない。
再び頭がクラクラとし、気づけばまた別の場面。木下は街を歩いている。酔い覚ましに風を浴びているつもりなのだろう。だが、歩くたびに見える景色はどこか不自然だ。
見慣れた街並みは変わらないが、音も匂いも曖昧だった。そしてクラクラとともに景色が変わる……
最後に気づいたのは再びベッドの上だった。今度こそ現実のようだ。だが、青いボタンがまたテーブルの上に置かれている。
木下は恐る恐るボタンを手に取り、じっと見つめた。そして思った。
「これを押すべきじゃないのかもしれない」
テーブルにそっと置いた。瞬きを一つ。今置いたはずのボタンはなくなっていた。その代わりに、冷めた味噌汁が置かれていた。
山田は笑ってつぶやいた。
「まったく、酒のせいだろうな」
だが、次に酒を飲むとき、ポケットに手を入れると、小さな青いボタンが転がっていた。