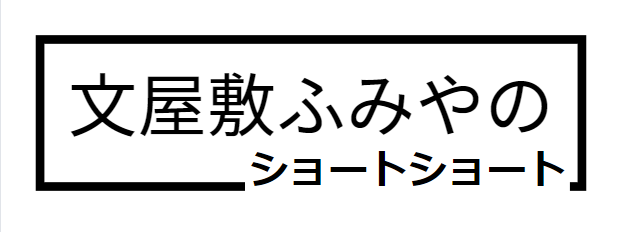自室の窓から空を眺める。澄み切った冬の青空にどうとも言葉にできない言えない感情を落ち着けていく。
友人の高貴から連絡が来たのがつい1時間前だった。言っていることがつかめず、とりあえず俺の家に来るように促した。
家の庭に自転車が止まった。俺は玄関に向かい彼がチャイムを鳴らす前にドアを開いて招き入れた。
「永弘。実は……僕はロボットかもしれない」悩んだようすでうつむく彼は、さながら教会の懺悔室のようだったが、ここは俺の部屋だ。
中学のころ、高貴に出会い何気ないことで友人になった。それから4年は経とうとしているが、彼にはどうも思い込みが強い傾向がある。不審者と出くわしたとき用に常に鞄にカッターを入れている時期もあったし、「実は両親と血がつながっていないかもしれない」と語りだすこともあった。そのたびに彼から一番に相談されては、アボカドの皮を剥くような忍耐力でゆっくりと時間をかけて、その考えを修正してきた。今回もそれをしなくちゃいけない。連絡の内容からそれはわかっていた。
「どうして、そう思ったのか。聞かせてくれるかい?」
「僕、Ⅱウィッターをはじめたくてさ。ほら最近リリースされた新しいSNSの。知らないの? まあいいや。でさ、アカウントを登録してたわけ、一通り個人情報を入力したら最後に写真を選ぶように指示されたんだよ。”あなたはロボットではありません”って問いにチェックを入れてさ。
6つの写真の中から消火栓が写っているものを全てにチェックを入れるように指示されてさ、2枚の写真を選んだんだ。でも、”正しくありません”って表記がでた。消火栓なんてめったに見るようなものじゃないからさ、見落としがあったんだとあきらめてまた挑戦したんだ。問いは一度きりだったみたいで今度は信号機を選ぶように指示された。これならと思って……。でもダメだった。信号機だけじゃない。それから車、ぬいぐるみ。何回やってもうまくいかなかったんだ」
「それで、”あなたはロボットではありません”を逆に解釈して自分はロボットだと思ったわけか」
「うん」
うーん、とうなり彼の長い話を整理する。解決策と説明をどうしようか。目を瞑り、5秒。まずは彼に起こったことは、ただのあるある探検隊的な話だと伝えて、この場でもう一度アカウント登録をしようと言った。
アカウントの写真選択画面では二人で見落としが内容に確認をして、無事アカウントを作ることに成功した。
彼は泣いていた。高校入試の合格発表で自分の数字を見つけた時のような、嬉し涙だった。俺は引いた。
長居することもなく、彼は家を後にした。ふぅ、と短いため息をつく。
だが、この問題はまだ解決してはいなかったらしい。
2週間ほど過ぎた、月曜日の放課後の教室。部活のない一斉登校の曜日に教室に残っているのは高貴と俺だけだった。
「やっぱり俺はロボットかもしれない」
「またか……」
今度は教室を懺悔室に代え語りはじめた。
それは日直帳のような無駄の多い話だった。
高貴はその日、珍しく母親に買い物を頼まれた。
「いつものお米をスーパーで買ってきてちょうだい。もしアーモンドカレーのルーがあれば、2つ買っておいて」
「わかった。すぐ行ってくるよ」
彼はすぐに近くのスーパーへ向かい、買い物を済ませ母親に品を渡した。買ったものを見た母親は「ちょっと」っと少し怒った表情で高貴に言葉を浴びせた。
「どうしてお米を2つも買ってきたのよ」「えっ、だって」
買ったものはお米を2袋だけだった。母親に問い詰められると彼はカレーのルーを見つけたからお米を2袋にしたといった。
その日、その一軒が夕食の場で話に上がったらしい。その際に高貴の父親が「プログラミングの世界でそういうジョークがあったな」と笑ったことで高貴の中に自分ロボット説が再燃したとのこと。
「いいかい」俺は高貴にタンポポの綿毛を飛ばさぬような優しい口調を務めて説明する。
母親の言葉が足りないこと。君も内容の確認をすればそういったミスにならなかったことを伝えた。
これは口にしなかったが、父親。余計なことを言うなとも思った。
「つまらない失敗は誰にでもある。君はロボットなんかじゃないよ」
「でも……」そう言って、彼は自分の手を頬に当てた。
「僕の手、夏なのに冷たいんだよ!」
「おまえの手はもともと年中冷たいんだよ」どうも彼は、自分はロボットだという理屈に何事もつなげたがるようになってきていた。
そして、1週間の月日が流れて、今は彼の家の自室。
思い込みが強すぎる彼がこのところ心配になり、放課後彼の家に久しぶりに遊びに来ていた。
「コレ、オチャデス。ドウゾ」
「ありがとう」
思い込みが強すぎる彼は時折口調もロボットみたいになっている。彼の思うロボット像が昭和だった。
お茶をすすりつつ、部屋を見渡す。本棚の中に『マンガで分かるロボット工学』『ロボットのロボットによるロボットのための哲学』など、ロボットという単語が目につく本がいくつか並んでいることに気が付いた。
「僕にはまだ人間らしい部分は残っているのだろうか」
問いかけに答える前に、ノックの音が3回響いて高貴の母親が顔を出した。
「ちょっと高貴ー。ジャージ早く出しちゃいなさいよ。帰ったら洗い物は出すのが約束でしょ! あら、永弘君、来てたの! ごめんなさいねお邪魔しちゃって。じゃあ高貴早くしなさいね」
「……今やろうと思ってたのにー!!」
友人の前であーだこーだと言われることに腹が立った高貴は、立ち上がって母親を追い出すようにドアを閉めた。
「すごく人間だよ。君は」