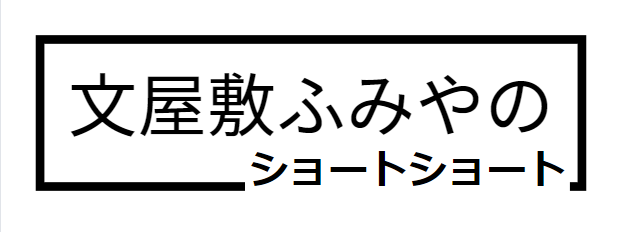徹が昼寝から起きて、日が沈みそうな時間に掃除をしていると、玄関のチャイムが鳴った。
ドアを開けると五円玉に紐を通した、いかにもなアイテムをぶら下げている彼女が立っていた。
「あなたはだんだんタキシードを着たくなーるー」
紐を持って五円玉を左右に揺らしながら彼女はつぶやく。
彼女の趣味は掃除に洗濯に催眠術。
家庭的な趣味の中に、スパイスのきいた趣味も持っている素敵な女性だった。
徹は部屋に戻り、そそくさとタキシードに着替える。
タキシードは、先週彼女が特に理由を説明せずに置いていったものだった。
徹はこういった、彼女の行動に馴れていた。彼女のやりたいようにやらせよう、というのが徹の座右の銘になっていた。
「あなたはレストラン○○に行きたくなーるー」
五円玉を揺らして彼女が次の命令をした。
座右の銘は車に乗り込んだ。
「でもあそこは予約が必要なお店じゃなかった?」
キーをまわそうとしたとき、徹は助手席の彼女にきいた。
「予約は済ませてあるわ」「なるほど」
車で走り出して、20分ほどで目的地に着いた。
「いらっしゃいませ」
案内に従いつつ、徹の手を引き彼女がテーブルへと座る。
コースメニューを食べ、二人は楽しいひと時を味わった。
食事がすむと、彼女は五円玉を取り出し、また催眠をかける。
「あなたは私にプロポーズがしたくなーるー」
「…………指輪がないや」
「指輪は後でいいわ。告白の言葉だけ」
徹は優しく彼女の手つかんだ。
彼女は驚いた様子でその大きな瞳をさらに大きくした。
「来週また今日と同じ場所でデートをしてほしい。その時に伝えるから」
ディナーの場所もプロポーズの場所もタキシードのレンタルまで全部かぶってしまった。
徹の計画より1週間は早く彼女が準備をしていた。徹はやっぱり僕たちは似たもの同士だと、笑みがこぼれる。
「やっぱり指輪はなくて正解だったわ」
彼女は全部を理解した様子でうなずくのでした。